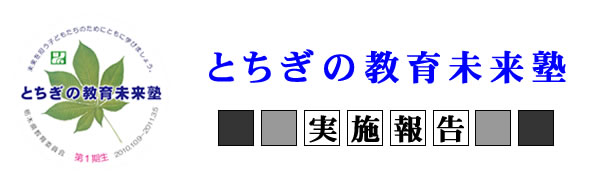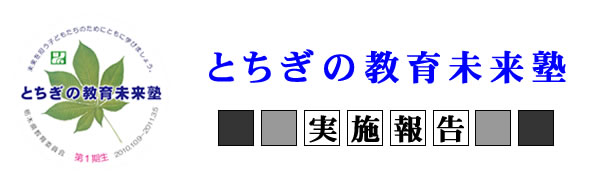
第9回 (2月19日)
講話「本県における児童・生徒指導」
生徒指導の意義や栃木県における「児童・生徒指導」という用語の意味、「学業指導」を充実させるための考え方等について確認しました。
 |
 |
| 講話の様子 |
- 受講者アンケートから
- 生徒指導とは、特定の生徒に対してのものだと理解していましたが、考えを改めさせられました。また、学校におけるいじめ、不登校なども、しっかりと背景を見極め、みんなで対応していくことが必要なのだと感じました。(現職の教員)
- 「学業指導」の充実、学びに向かう集団づくりの話の中で、「個人の成長は集団があってこそ」という言葉が印象に残りました。友達の姿を見て励まされたり、自分の欠点に気付いたりすることが、自分でもあるからです。互いに高め合う学級(集団)づくりを目指したいです。(現職の教員)
- 児童・生徒指導の対象は、すべての児童生徒であるというところがポイントであると思いました。それぞれの子どものよさ、個性を伸ばし、社会に出ていく上で必要な力をしっかりと身につけさせられる教員を目指したいです。(学生等)
- 埼玉県で学ぶ現在、「児童指導」という言葉を耳にする機会がないので、今日知ることができてよかったです。発達課題の視点から児童・生徒指導を考えることは新鮮でした。(学生等)
講話・演習「学校で生かせるレクリエーションの指導法」
レクリエーションの機能や効果等についての説明の後、「レクリエーションの指導に必要な力をどうとらえるか」というテーマでワークショップを行いました。