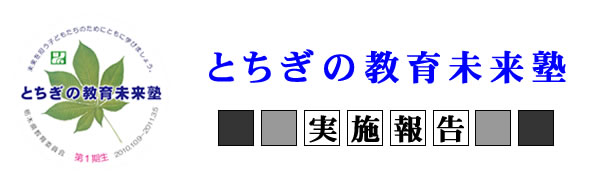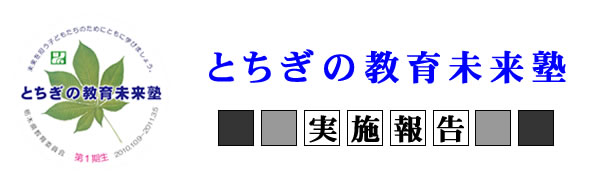
第7回 (1月15日)
講話「帰国・外国人児童生徒教育への対応」
帰国・外国人児童生徒教育の現状についての説明の後、学級への受入れ体制づくりや日本語指導の在り方等について学びました。
 |
| 熱心にメモを取る受講者の皆さん |
 |
 |
| 日本語指導の実際 |
- 受講者アンケートから
- 帰国・外国人児童生徒の思いを受けとめ、不安や心配を少なくしてあげられるよう、受入れの体制を工夫することが大切だと思いました。言葉も文化も生活様式も違う国で、一人で学校に通うことはとても負担になると思います。自分も学級も学校も、その子が安心して生活できるように配慮することが大切だと思いました。(現職の教員)
- 講話を聞いて、自分が考えている以上に、手助けを必要としている子どもがたくさんいることに驚きました。私も含めもっと周りの人が「国際社会への対応」を行動に移していく必要があると感じました。今回の講話で、さらに興味をもったので、もっと自分なりに調べてみようと思いました。(現職の教員)
- 講話を聞き、「帰国・外国人児童生徒」が日本の学校に入る以前に送っていた生活、環境、教育体系をしっかり把握、理解した上で、一人一人に合った指導をすることがとても大切だということを学ぶことができました。(現職の教員)
- 私は、帰国・外国人児童生徒への対応について、どのようにしていけばよいのか全く分からなかったのですが、今回の講話を通して、子どもたちとのかかわり方や言葉の教え方などを知ることができ、とてもよかったです。特に、遊びを通して言葉を教えるというところが実践的で、勉強になりました。(学生等)
- つい、言葉や生活習慣についてのみ考えてしまう「帰国・外国人児童生徒教育」ですが、一番考えなければいけないのは、子どもの心の不安や悩みだと感じました。帰国子女や外国人などを受け入れるあたたかい雰囲気づくりは教師の大切な役目だと思いました。(学生等)
講話・演習「今、求められる道徳教育」
道徳教育の意義及び目標、道徳教育における教師の役割等について講話がありました。その後、先達の言葉をもとにして、それぞれの教育観について考えました。