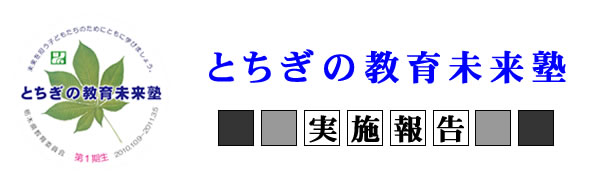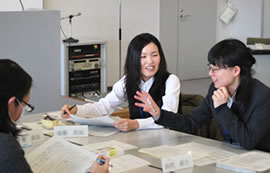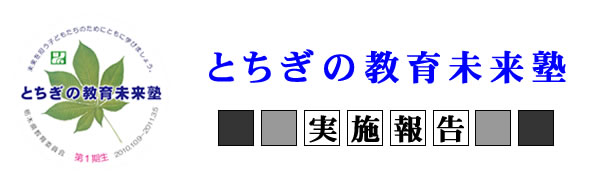
第8回 (1月22日)
講話「道徳の時間の授業の在り方」
「道徳の時間」の役割や基本的な学習過程等について、実際の授業のDVDを視聴しながら確認しました。
 |
 |
| 講話の様子 |
- 受講者アンケートから
- ポイントを絞って説明してくださったので、授業を組み立てる際に何に気をつけたらよいか、分かりやすかったです。また、実際の授業の様子を見られたことでイメージが深まり、とてもよかったです。子どもがすんなりと自分に置きかえて考えていく場面で、教師の発問が重要であることを感じました。(現職の教員)
- これまで、道徳の授業の展開の仕方や授業の在り方は難しくて苦手だなと感じていたのですが、講話を聞いて、今度は学んだことや知ったこと等を生かして、こんなふうに授業をしてみたいという気持ちになりました。(現職の教員)
- ねらいを明確にし、それに沿った発問によって子どもたちの価値観を引き出すだけでなく、そこから現実にある出来事に応用できる考え方へとつなげさせることが大切だということを学びました。(現職の教員)
- 高校では道徳の授業がないので、とても参考になりました。教師が生徒一人一人と向き合い、言葉を引き出していく方法はとてもためになりました。キャッチボールをすることで、生徒の考えを確立させていっているのがよいと思いました。(現職の教員)
- 道徳の授業の展開の仕方を知らなかったので、この講話はとてもためになりました。授業をする際、どの部分に着目させるのか、授業をやる側として明確に自覚していないと、生徒に伝えられないと再確認しました。(学生等)
- 大学で道徳の時間の授業について学んでいますが、資料から「ねらい」をしっかりもつことがなかなか難しく、どのように授業を考えればよいのかが分かりませんでした。講話を伺って光が見えてきました。(学生等)
演習「道徳の時間の授業の実際」
示された資料をもとに、各班で学習指導案を検討し、ポイントとなる場面を取り上げて模擬授業を行いました。