平成23年度 第2期「とちぎの教育未来塾」 実施報告 第6回
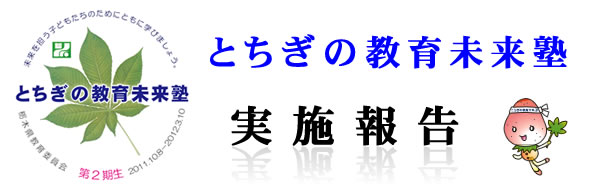
第6回 (12月17日)
講座「特別活動の意義と各活動の指導」
 |
|
 |
 |
| 講話の様子 | |
- 受講後のアンケートから
- よい思い出、楽しかった思い出の裏には、教師のよい指導・支援があったのだということに改めて気付かされました。私も、子どもたちがずっと心に残すことのできるよい思い出をつくってあげられるよう、ねらいをもって指導・支援していきたいと思います。(現職)
- 学級活動やクラブ活動、児童会活動、学校行事など、子どもたちにその活動を通してどんな力を身に付けさせたいか、どんなことを考えさせたいか、どのような気持ちを高めたいかをしっかり意識して指導や支援をしていきたいと思いました。(現職)
- 自分の学生生活を振り返り、当時の先生の姿を思い出しながら考えていくことができ、当時では気付かなかった、先生のねらいや願いはこうだったのかなあと感じました。また、毎回痛感していることですが、現職の先生方の考えが大変具体的で、とても勉強になっています。(学生等)
- 特別活動の目的については大学で学習しましたが、あまり具体的なヴィジョンが浮かんでいませんでした。今回の講話で、特別活動における細かい目標や何のために指導を行えばよいのかということについて理解することができました。(学生等)
神長善次氏による特別講座「陶知技教意苦感」
講話の題である「陶知技教意苦感」には、「陶冶」「知識」「技能」「教習」「意思」「苦悩」「感動」といった意味が込められており、それらが発達段階に応じて、例えば、「知見」「知識」「理知」と変化していくという内容のお話がありました。
その上で、欧米、中国、インド、イスラーム、そして日本では、それぞれどの側面が重視されているかという、長年外国でお仕事をされていた神長氏ならではのお話がありました。
さらに、中禅寺湖畔に立つトチの大木の例から、環境の重要性等についての御指摘がありました。
 |
 |
| 講話の様子 | |
 |
| 神長氏、県教育長、総合教育センター所長を囲んでの全体写真(前半の班) |
 |
| 神長氏、県教育長、総合教育センター所長を囲んでの全体写真(後半の班) |
- 受講後のアンケートから
- 教育について、国際的な視点からお話しいただき、大変参考になりました。教育現場の中に入ってしまうと、どうしても視野が狭くなってしまうので、今回の御講話を聞き、日本に生まれた子どもたちを世界的に通用する人間に育てるという視点をもつことも大切だと感じました。(現職)
- 教育に対する心構え、考え方に留まらず、個人としての生き方にまで踏み込んだお話で、とても考えさせられました。生徒と向き合う上での大切な示唆を得ることができた講座でした。(現職)
- 聞き始めはすごく難しいもののように感じてしまいましたが、徐々に一つ一つの要素がつながって、「教育」という大きな括りの中の各要素であることが分かりました。私も巨木をつくる教育者の一人となれるよう、苦節に耐えてさらにがんばりたいと感じました。(学生等)
- 自分では全く考えもしなかったユニークな視点からの教育の在り方の分析を拝聴することができ、目からうろこが落ちる思いでした。特に、日本の教育と諸外国の教育の比較について、大変勉強になりました。(学生等)

