平成23年度 第2期「とちぎの教育未来塾」 実施報告 第3回
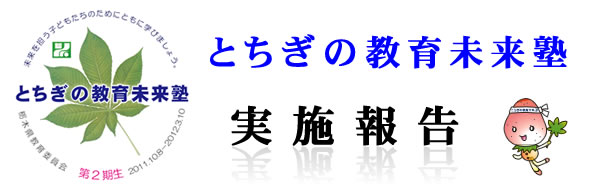
第3回 (11月5日)
講座「学校における教育相談」
 |
 |
 |
 |
| 演習の様子 | |
- 受講後のアンケートから
- 子どもの話を聴くときは、子どもの言葉の裏にある本当の思いや気持ちなどを汲んであげられるように、子どもの心に寄り添って聴いてあげたいと思いました。(現職)
- 子どもたちがどんな相手だったら話しやすいのか、どんなふうに聴いたら話しやすいのかを体験することで実感することができました。うなずき、共感的理解などの大切さも改めて感じました。(現職)
- 目を合わせて、うなずいて聴いてもらうことが、こんなに安心できる、受け入れられている雰囲気をつくるとは思いませんでした。今まで、何か作業をしながら、子どもの話を聴いてしまうことがあったので、忙しいときでも、作業をやめて、きちんと話を聴こうと思いました。(現職)
- わかろうとする姿勢が重要であるというのは、様々な書籍で見かけますが、逆に「わかろうとしない姿勢」がどれだけ子どもの心を傷つけ、相談しようとする気持ちをなくさせ、教員を信頼できなくさせるか、ということを演習を通して自分で体験し、気付くことができました。(学生等)
- 「話を聴いてもらえる」ということが、こんなにもうれしいものだと思いませんでした。教師の「聴く」姿勢が子どもの安心感、信頼感につながっていくことを改めて感じました。(学生等)
講座「発達障害のある子どもの理解と支援」
|
||
|
||
班別研究協議の様子 |
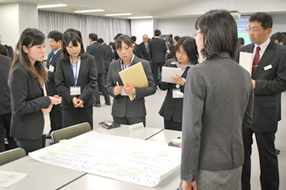 |
 |
ポスターセッション形式の各班の発表 |
|
- 受講後のアンケートから
- 支援の必要な子どもを特別視するのではなく、支援の必要な子どもにとっても、学級の友達にとっても居心地のよい学級であるような工夫が必要であるということがとても心に残りました。(現職)
- 発達障害があるからではなく、発達障害があってもなくてもすべての子どもに対してわかりやすさ、安心感を意識して関わることが大切だということがわかりました。発達障害のある子どもへの支援というと難しくて大変なイメージがあったのですが、困難な状況を乗り越えられるように自信を育てることだと考えるとわかりやすいと思いました。(現職)
- 様々な班の発表を聴いて、共通して「誉める」「認める」といった言葉を聞きました。自分が教師になったときに、障害をもった子どもを認め、できることを見つけて増やしてあげることを大切にしたいと思いました。(学生等)
- 障害となると特別扱いをしてしまいがちですが、障害を一つの個性ととらえ、その子どもが自信をもてる、クラスみんなが一人一人を認め合える環境が大切なのだと感じました。そのためには、教師が先頭に立ってその子どもをきちんと理解し手助けをしていかなければなりません。連携して、障害のあるなしにかかわらず、のびのびと過ごせる環境をつくっていけるようにしていきたいです。(学生等)





