 普通教科「情報」の指導と評価について
普通教科「情報」の指導と評価について
< 前のページ □□ 次のページ >
3 評価規準について |
| 学習指導要領に示された目標や、評価の観点の趣旨を踏まえて指導を行い、目標が達成されたかどうか目標に準拠した評価を行う場合、「おおむね満足できる」と判断される学習の実現状況を示したものが評価規準です。この実現状況を評価するにあたっては、内容のまとまり全体を通して判断されるものであるため、その根拠をたくさん用意しておく必要があります。実際の評価活動は、学校ごとに使用する教科書や実施する学習活動などの違いもあり、具体的な学習活動に即した評価規準を作成する必要が出てきます。国立教育政策研究所でも、「評価規準、評価方法等の研究開発」が進められており、平成15年9月に「高等学校における評価規準、評価方法等の研究開発について(中間整理)」が出されました。また、本調査研究では、各研究協力校で作成した評価規準を資料編に例示しました。各学校においては、これらの資料を参考に、各校の学習活動に即した評価規準を作成してください。 |
<作成上の留意点> |
| ① 生徒の学習状況を適切に評価できるような評価項目にする。 ② 指導の改善及び生徒の学習の改善に生かせるようにする。(指導と評価の一体化) ③ 評価項目を細かく設定しすぎて教員にとって過大な負担とならないようにする。 |
| 図5は、指導と評価の一体化におけるPDCAのマネージメントサイクルと評価規準との関係について模式的に表したものです。 |
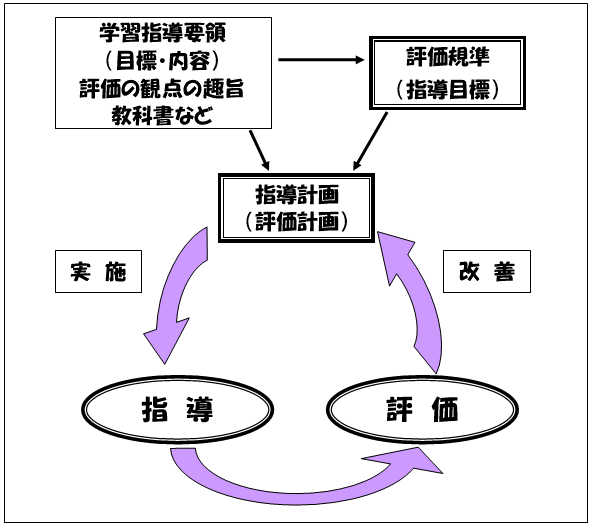 |
図5 指導と評価の一体化のPDCAサイクル |
