 普通教科「情報」の指導と評価について
普通教科「情報」の指導と評価について
< 前のページ □□ 次のページ >
| 2 指導計画における実習の位置付けとその展開 |
| (1) 実習の目的 |
| 普通教科「情報」では、実践や体験のための活動を「実習」といい、学習の中では重要な位置付けとなっています。現実的、実際的な課題を取り扱うことで、興味・関心を高めたり、学習した内容を自己評価させ、それを改善させる活動を取り入れることで、自己学習力を育成することが大切です。図2に、実習の目的とその方策を示しました。 |
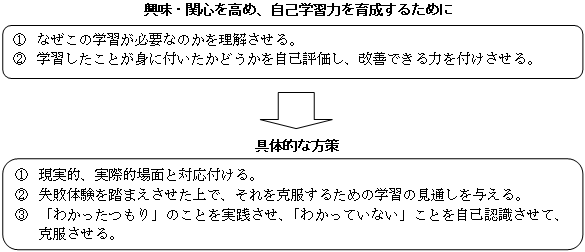 |
| 図2 普通教科「情報」における実習の目的とその方策 |
| (2) 実習の流れとその考え方 |
| 導入では、「情報の科学的な理解」への動機付けをしながら、体験的活動を通して中学校までに習得した「情報活用の実践力」の基礎固めをします。その後、「情報の科学的な理解」に重点を置きながら、それを実習によって「情報活用の実践力」へと転換させていきます。さらに、「情報の科学的な理解」を基礎として「情報社会に参画する態度」を育成し、その両者を結びつけながら「情報活用の実践力」をさらに高め、定着させていきます。 次ページの図3のような流れに沿った実習は、年間の授業を通して計画的に実現すると同時に、一つの単元や1時間の授業の中でも実現することがポイントです。 |
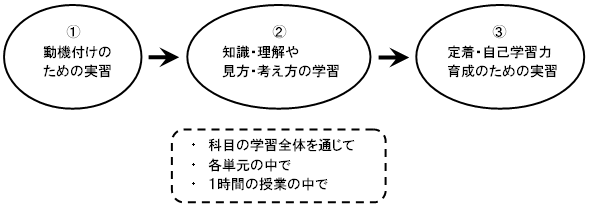 |
| 図3 実習指導の流れ |
| ①動機付けのための実習 |
| 動機付けのため実習は、その後の学習に向けた問題提起を行い、学習の見通しを示すための実習です。学習内容を総合化して、基本的な見方や考え方が必要であることを認識させます。また、自己流のやり方や考え方の欠点を認識させることも重要なポイントです。したがって、この段階では詳細な技術的内容を知識として教え込むようなことは適切ではありません。 |
| ②知識・理解や見方・考え方の学習 |
| ①の動機付けのため実習を受けて、「知識・理解や見方・考え方の学習」となります。「見方・考え方の学習」とは、日常的な問題解決に役立つ見方・考え方を学ぶとともに、それらを情報の処理や伝達という観点で捉え、解決する方法を学ぶことです。したがって、この段階でも、技術的な解説を詳細に取り扱うのではなく、「見方・考え方」を養えば、情報技術の効果的な活用に自然に結びつくという考え方で実習を組み立てることが重要です。 |
| ③定着・自己学習力育成のための実習 |
| ②で獲得させた見方・考え方を、より広範な問題解決に適用できるようにするために、より具体的、実践的な活動を行う段階です。したがって、この段階では、生徒の実態を考慮した上で、①、②の段階との共通性を保ちながら、多様性や自由度の高い課題について取り組ませることがポイントとなります。 |
| (3) 実習と座学との連携 |
| 普通教科「情報」においては、「情報A」では2分の1以上、「情報B」、「情報C」では3分の1以上を実習に配当することとされていることは前に述べました。これは、実習と座学とを連携させた指導を想定したものです。たとえば、前項目の「①学習の動機付けを行うための実習」は、座学の前に行うべきもので、学習内容への興味・関心を高めたり、学習目標や課題を明確にしたり、学習の進め方を示したりするために行います。また、「②知識・理解や見方・考え方の実習」と「③定着・自己学習力育成のための実習」は、座学で学習した内容を実際に課題解決に応用して、知識の適用の仕方やその効果を確認させたり、今後の学習の方向性をもたせたりするための実習となります。 このように、指導計画を作成するに当たっては、実習の目的の違いを配慮し、座学との連携を十分に配慮する必要があります。 |
