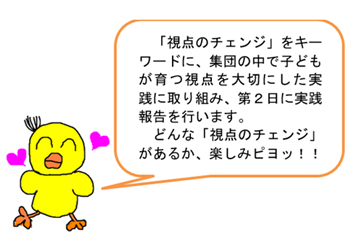目
的 |
障害のあるなしにかかわらず、共に生活し学ぶインクルーシブな保育の在り方について理解を深め、一人一人と集団が育ち合う保育を実践する力の向上を図る。
|
日
時 |
令和 6年 6月27日(木) 9:30~16:00
|
対
象 |
幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校、特別支援学校教職員、保健師
|
研
修
内
容 |
1 説明「研修の概要~視点のチェンジ~」
2 講話「子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育」
3 実践発表「一人一人と集団が育ち合う保育の実際」
4 情報交換「第2日の実践報告に向けて」
|
講
師 |
宇都宮大学大学院教育学研究科 准教授 司城紀代美 氏
認定こども園釜井台幼稚園 園長 山﨑 英明 氏
認定こども園かしわ幼稚園 保育教諭 小笠原礼佳 氏
那須町伊王野保育園 保育士 藤田 健一 氏
総合教育センター職員
|
研
修
の
様
子 |
|
|
|
|
講話「子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育」
|
|
|
|
|
実践発表「一人一人と集団が育ち合う保育の実際」 |
|
|
|
| |
|
研
修
評
価
・
振
り
返
り
シ
|
ト
か
ら |
○ 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。
|
|
そう思う
|

|
そう思わない
|
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
| 幼稚園 |
6 |
66.7% |
3 |
33.3% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| こども園 |
17 |
81.0% |
4 |
19.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| 保育所 |
31 |
86.1% |
5 |
13.9% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| 小学校 |
7 |
100.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| 特支校 |
3 |
60.0% |
2 |
40.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
| 合計 |
64 |
82.1% |
14 |
17.9% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
○ 日頃の実践について振り返ったことや今後の実践に生かしたいこと
- 一人一人のよさや可能性よりも、自らの困り感や集団に入れなくてはいけないという大人の都合を子どもたちに押し付けてしまいがちであったと反省した。子どもたちと改めて出会い直し、長い目で楽しみながら保育をしていきたい。
- 保育者としてその子自身の支援をしようと急いでしまっていた。その子どもと他の子どもの関わりを、ゆったりと見守り、どんな関わり方があるだろうかと考えながら、回り道をたくさんして一緒に進んで行きたいと思った。
- 毎日、慌ただしく保育している現状で、立ち止まって考えたり考えさせられたりという、有意義な時間となった。今後の課題や試してみたいことができたので、現場で生かしていこうと思う。
- 「出会い直し」という言葉に感銘を受けた。日々の忙しい保育の中で、一度落ち着いて子どもと向き合い出会い直しをすることで、よいところや気づかなかったところを発見できると思った。
- 日々の保育の中で、どのくらい子どもの声や思いに耳や心を傾けられていたのかを振り返り、反省した。これからは、それぞれの思いや友達とのやりとりで遊びや活動を展開していけるよう見守り、サポートしていきたい。
- 子ども一人一人のよいところをたくさんみつけ、カラフルな色で溢れた園の環境を整えられるよう、保育者同士で意見を交換したり、一緒に考えたりしながら園全体の雰囲気を良くしていけるようにしたい。子どもとの関わりを見直したり、考えたりするとてもよい時間となった。
- 保育歴が長くなるにつれ、考え方や支援の仕方も疑問視することなく日々が過ぎていたことに改めて気付かされた。もう一度、一人一人の子どもたちと出会い直し、視点を変えていくことで子どもの気持ちに寄り添うことを心掛けたいと思う。また、集団の在り方も見直し、誰もが笑顔でいられる保育を行いたい。
- 子どものよさや可能性に目を向けた支援ができるようになりたいと改めて感じた。障害の特性に合わせた支援ではなく、その子に合った支援を心掛けたいと思う。幼児期を担当している先生との情報交換は新鮮で、小学校現場にも通じるものが多いと感じた。
- 小学校に入学してくる子どもや保護者に、「小学校の壁」を感じさせないようにしたいと日々心掛けている。1年生担任だけでなく、教職員全体で幼児期の子どもの姿を知り、成長を見守っていける体制作りをしていけたらと思う。
- 特別支援学校に勤務しているので、個に応じた見方や支援方法等を見出すことは身に付いており、実践できていると思う。今回、幼児教育の話を聞いて、集団の中での学び合いという視点に気付いた。特別支援学校でも集団の中での学び合いをしていく視点が大切であり、意識していきたいと思った。センター的機能として、夏季休業中に勤務校で地域の幼保小の先生向けの研修を行うので、今回の研修で得た知識や経験を生かして話をしていきたいと思った。
- 園の巡回相談では、「子どもの困り感」か「先生の困り感」なのか、その問題を整理できるようにしている。子どもの困り感の背景には、発達段階、取り巻く環境、周囲の関わり方等が相互に影響し合っていることを考慮し、行動の要因を考えられるようにしている。その際、必要な視点がまさに「視点のチェンジ」であることが再確認できた。子どもの発達に喜びや希望をもち、多面的、多角的に子ども捉えていけるよう研鑽していきたい。
|
 研修
研修