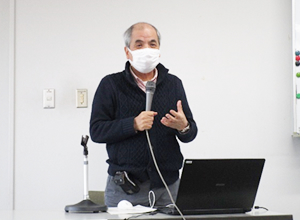目
的 |
障害のある子どもなどの保育の在り方について理解を深め、指導力の向上を図る。
|
日
時 |
令和4年12月 6日(火) 9:30~16:00
|
対
象 |
幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校、特別支援学校
教職員、保健師
|
研
修
内
容 |
1 実践報告・協議「視点のチェンジ~事例から学ぶ~」
2 講話「2日間の研修を振り返って~子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育~」
3 講話「インクルーシブ教育~子どもの多様性が活き仲間が育ち合う保育~」
|
講
師 |
宇都宮大学大学院教育学研究科准教授 司城紀代美 氏
東京都立大学名誉教授 浜谷 直人 氏
|
研
修
の
様
子 |
|
|
|
|
実践報告・協議「視点のチェンジ~事例から学ぶ~」
|
|
|
|
|
講話「2日間の研修を振り返って~子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育~」
|
|
|
|
|
講話「インクルーシブ教育~子どもの多様性が活き仲間が育ち合う保育~」
|
|
研
修
評
価
・
振
り
返
り
シ
|
ト
か
ら |
○ 本日の研修は、今後の職務に生かせる内容でしたか。
|
|
そう思う
|

|
そう思わない
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
未回答 |
|
満足度・活用度
|
幼 |
7 |
87.5% |
1 |
12.5% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
| こ |
19 |
86.4% |
3 |
13.6% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
| 保 |
17 |
85.0% |
3 |
15.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
| 小 |
7 |
100.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
| 特 |
2 |
100.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
| 全体 |
52 |
88.1% |
7 |
11.9% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0 |
○ 日頃の実践について振り返ったことや今後の実践に生かしたいこと
-
視点のチェンジによって、子どもの力を信じ可能性に期待することで、子どもの遊びや生活面の活動の幅が広がった。私自身も保育が楽しくなった。インクルーシブ教育については子どもが楽しむことの重要性を学ぶことができたが、関わる私自身が楽しむことで子どもたちの成長へと繋がると感じた。
-
保育をしていく中で視点のチェンジを常に意識していきたいと思った。実践報告を通して他の園や特別支援学校の先生とも話す機会ができ、様々な視点のチェンジを知ることができた。この研修を通して一つの考えなどにはとらわれず、子どもの抱える背景や思いを受け止め温かく包み込めるような保育者になりたいと思った。
-
子ども同士の関わりから、その子の良さを見取り、子どもたちの力を信頼しながら見守っていくことの大切さを改めて感じた。また、保育者の焦る気持ちは過剰な支援へと繋がる、なんとかしようとするのではなく、様々な人の目で、長い目で見守ることの必要性と重要性を感じた。子どもたちにとって「楽しい」「嬉しい」と感じられるような体験、成功体験を重ねて、自己肯定感を高めていけるような保育を展開していきたい。子どもたちのこれからの長い人生の土台を形成していく上で、今を大切にしながらも先を見据えて、子どもたちと一緒に楽しみながら様々な活動に取り組んでいきたい。
-
「試行錯誤した支援がうまくいかないのではなく、子どもが成長して新たな課題が出てきたと捉える」という言葉に納得した。どんな反応にも「そうきたか〜」と何でもみんなで一緒に楽しめる保育をしていきたい。子どもたちの中に、心が温かくなる記憶をたくさんつくってあげたいと感じた。
-
普段の保育の中で、子どもをたくさん褒めようと努めていたが、何気ない言葉掛けにも自己肯定感を危ぶむ場合があることに気付かされ、はっとした。自分はそんなつもりはなかったが、子どもたちの中には評価を期待してしまい褒められようと動いてしまう子もいたのかもしれない。何気ない言葉にも気を付けて保育をしていきたいと改めて感じた。
-
「その人にはそうせざるを得ない何かがある」の言葉を思い出して生活できたら、迷いや悩みが軽減されると思った。これからも、子ども同士の関わりを大切に子どもを信じて支援していきたい。
-
就学前の子どもたちの様子や保育者の工夫を知ることができた。また、年齢が違っても支援を必要とする子どもの困り感や周りにある環境などの課題は共通するものがあると感じた。心の充実や良質な記憶などの子どもの望ましい体験がその時の子どもだけでなく、その後の人生にも大きく影響するということが分かった。子ども一人一人を大切にし、またそれを子ども自身に伝えて大切にされているという自覚をもたせてあげることの重要性に気付くことができた。
-
特別支援学校は子どもと個別に関わることが多いが、改めて集団での学びの大切さを実感できた。また、障害名やできるできないで子どもを決めつけないこと、子ども自らの育ちを大切にすることを再確認できた。今後の支援に繋げていきたい。
|
 研修
研修