| 目 的 |
生徒指導主事の職務・役割、生徒指導上の諸問題等についての理解を深め、生徒指導主事としての資質の向上を図る。 |
| 日 時 |
平成23年6月20日(月) 9:30~16:00 |
| 対 象 |
高等学校、特別支援学校の新任生徒指導主事 |
| 研修内容 |
1 講話「不登校の理解と支援」
2(1) 事例研究「組織的な指導体制の在り方-いじめへの対応-」(高)
(2) 研究協議「特別支援学校における児童・生徒指導上の課題と指導の在り方」(特)
3 講話・演習「ネットトラブルの予防と対策」
4 講話「関係機関との連携」
|
| 講 師 |
総合教育センター教育相談部副主幹
総合教育センター研究調査部指導主事
宇都宮少年鑑別所所長
|
| 研修の様子 |

講話「不登校の理解と支援」 |

事例研究「組織的な指導体制の在り方」(高) |

講話・演習「ネットトラブルの予防と対策」
|

講話「関係機関との連携」 |
|
| 研修評価・振り返りシートから |
- 0 研修の満足度、研修へのニーズ
- 満足度
| |
満足 |
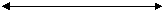 |
不満足 |
| |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 研修満足度 |
38.1% |
57.1% |
4.8% |
- |
- 研修ニーズ
- 性に関する問題行動への対応
- 各学校における生徒指導上の問題点と具体的な対策についての情報交換
- 道路交通法や高校生の交通事故の事例
- 1 講話「不登校の理解と支援」
- 【研修の目標】
| 学校全体で取り組む不登校の予防と支援について理解する。 |
- 【講話を聞いての主な意見・感想】
- 不登校対策の段階的な指導において、一次対策や二次対策の大切さが理解できました。
- 登校できる条件としての心のエネルギーの充足や社会的能力の大切さが理解できました。
- 特別支援学校は、障害との関係で、選択できる学校が少なく、進路変更も難しいです。そのため、不登校は重大な課題になってくると思います。学校全体で不登校対策に取り組む必要性を感じました。
- 2 (1) 事例研究「組織的な指導体制の在り方-いじめへの対応-」(高等学校)
- 【研修の目標】
| 事例研究を通して、危機管理における組織的な指導体制を図るための生徒指導主事の役割を理解する。 |
- 【事例研究を実施しての主な意見・感想】
- 組織としての対応、連絡調整する立場としての具体例を確認することができ、大変有意義でした。
- 組織的な対応や職員全員による支援、予防的生徒指導の重要性に気付きました。
- 生徒指導主事は組織的な対応や保護者との連携などの中心となるので、多面的な情報を整理しながら、今後の指導に取り組みたいと思います。
- (2) 研究協議「特別支援学校における児童・生徒指導上の課題と指導の在り方」(特別支援学校)
- 【研修の目標】
| 生徒指導上の課題について現状を分析し、情報交換を行い、組織的な指導体制の在り方を模索する。 |
- 【研究協議を実施しての主な意見・感想】
- 各校が直面している課題は様々で、事例ごとに情報交換できたことは良かったです。
- 具体的な課題についての協議だったので、指導の取組体制や方法、外部機関との連携など、大変参考になりました。
- 他校で実際に直面している問題や、その具体的な対応策を知ることができ、大変参考になりました。
- 3 講話・演習「ネットトラブルの予防と対策」
- 【研修の目標】
| 生徒が日常触れているネット上の情報を体験することにより、誘発されるトラブルやその予防策について考えられる。 |
- 【講話・演習を通しての主な意見・感想】
- 聴覚に障害がある生徒にとって、携帯電話やパソコンは重要な情報源であり、コミュニケーションツールです。そのために、しっかりと情報モラル教育をしていかなければならないと感じました。
- いじめに発展させないため、生徒が犯罪に巻き込まれないために、生徒自身に情報モラルを身につけさせる指導が必要であり、同時に家庭と連携しながら、携帯電話やパソコンの使用について共通理解を図ることが重要であると感じました。
- 4 講話「関係機関との連携」
- 【研修の目標】
| 少年鑑別所の機能と役割について理解するとともに、学校と少年鑑別所との連携の在り方について理解する。 |
- 【研修の様子等】
- 研修後に実施したアンケートによると、「少年鑑別所の機能と役割について」高い理解度が得られました。非行少年に共通する環境として、家庭環境の不安定さがあるという事実を、統計に基づいて指摘されるなど、分かりやすい資料を用いて、丁寧に説明していただいたことが受講者の理解を促したようです。
|




