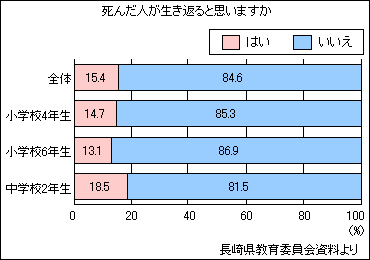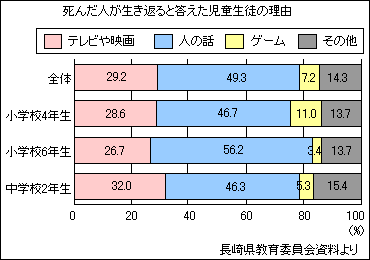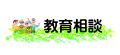コンピュータグラフィックスや音響効果を組み合わせて、人工的に現実感を作り出す技術のことです。
単に「人工的な現実感」といった場合には、例えば小説や映画といったメディア表現も含まれます。仮想現実の構成要件としては以下の4要素が必要(2~4の3つを構成要件する場合もあります。)とされます。
- 体験可能な仮想空間の構築
- 人間の感覚に働きかけて得られる没入感
- 対象者の位置や動作に対する感覚へのフィードバック
- 対象者が世界に働きかけることができる対話性
この基準に照らせば、例えば小説には視聴覚による没入感が欠け、映画には対話性が欠けるため、仮想現実とはみなされません。
テレビゲームの普及により、スイッチ一つで登場人物を殺したり、生き返らせたりすることができるゲームが子どもたちの間に普及してきました。これらは仮想現実の代表格です。
さらに、インターネットの普及により、顔の見えないコミュニケーションが主体となってきました。
下のグラフは、長崎県「児童生徒の「生と死」のイメージに関する調査の結果です。
|
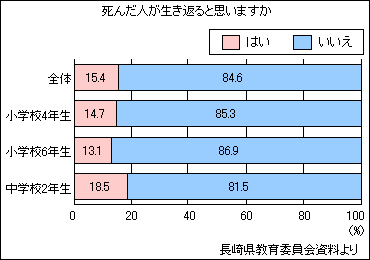 |
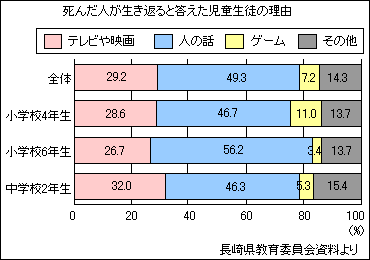 |
テレビゲームやネットゲームでは、一度死んだ人もリセットされ生き返りますが、現実社会では不可能なことです。情報社会の急激な発展のため、仮想現実と現実社会が接近して、区別しにくい時代になってきました。
仮想現実でも、人に迷惑をかけないこと、他人を思いやる気持ちを持つことを、そして、自分の行動に責任を持つことを忘れないで行動しましょう。
|
|