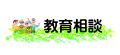平成15年11月に、当センターでは、シラバス作成と学習指導改善の参考資料として、「高等学校におけるシラバス作成のポイント」を発行しました。その続編として、このほど、研究協力校における実践研究の成果と課題を踏まえ、シラバスの活用を推進する具体的な方策をまとめました。また、平成15年11月の参考資料で紹介できなかった教科・科目や新たに内容及び形式を工夫した事例を示しました。
現在、各学校では、基礎・基本の徹底を図るとともに、生徒の主体的・自律的な学習を推進して、これまで以上に、生徒一人一人の能力を十分に伸ばすことをめざした教育を展開しようとしています。シラバスの導入は、学力向上に向けた取組を推進する重要な手だてとして期待が高まっています。シラバスの作成及び活用のねらいを明確にして、実践にあたることは、各教科の授業の質的な向上につながるとともに、保護者や地域の人々が学校の教育目標や教育計画などを一層理解するようになり、学校の説明責任を果たしたり、協力を得るための基盤づくりとなったりします。
このように、シラバスの果たす役割に対する期待がある一方、生徒の利用を促したり、内容及び形式の改善を進めたりする上で、いくつかの課題が指摘されています。それぞれの教科・科目などの担当者が、試行錯誤しながら主体的に課題の解決に向けて努力していくことが必要ですが、学習指導の全体計画や実行計画についてもシラバスに示すなど、学校経営の立場からシラバスを積極的に活用しようとする具体的な取組を推進していくことが大切です。これらの目的を達成するために、多くの事例や具体的な活用の考え方を知ることも重要です。本資料が各学校でのシラバスの作成及び活用の推進の一助となることを望みます。
平成16年3月
栃木県総合教育センター所長
豊田敏盟
|
 |

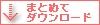 (PDFファイル:4.19MB)
(PDFファイル:4.19MB)